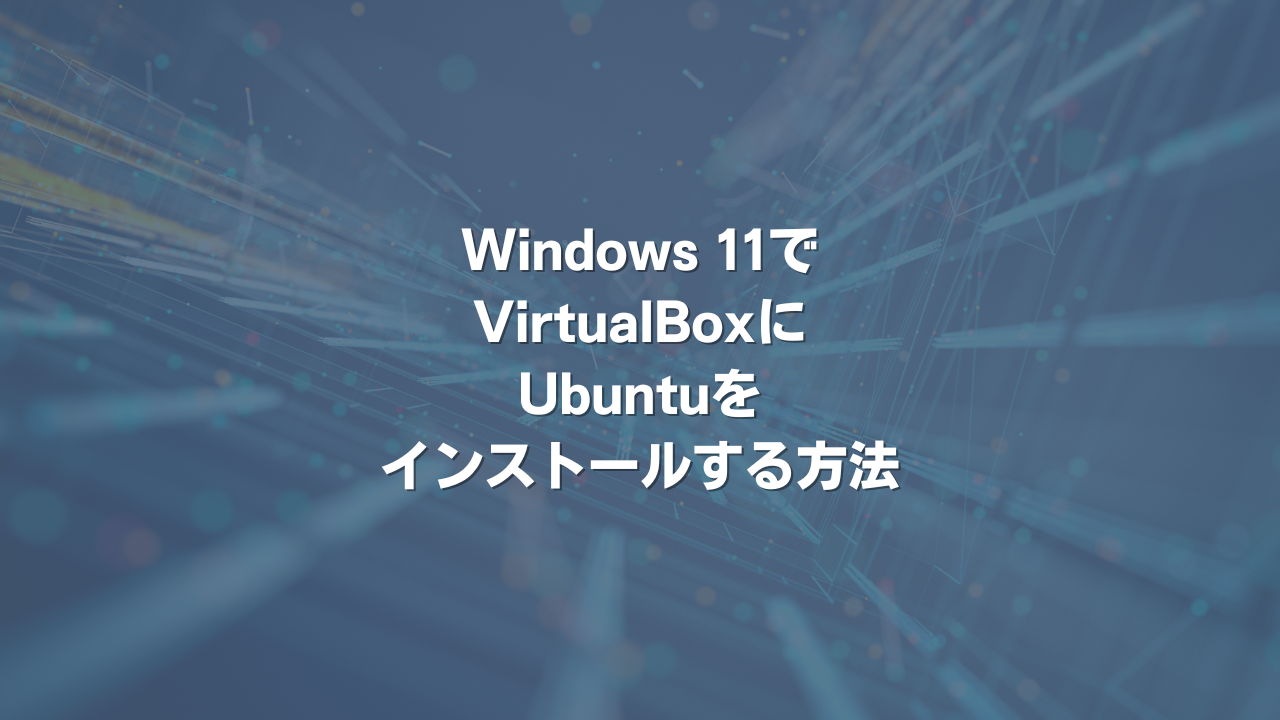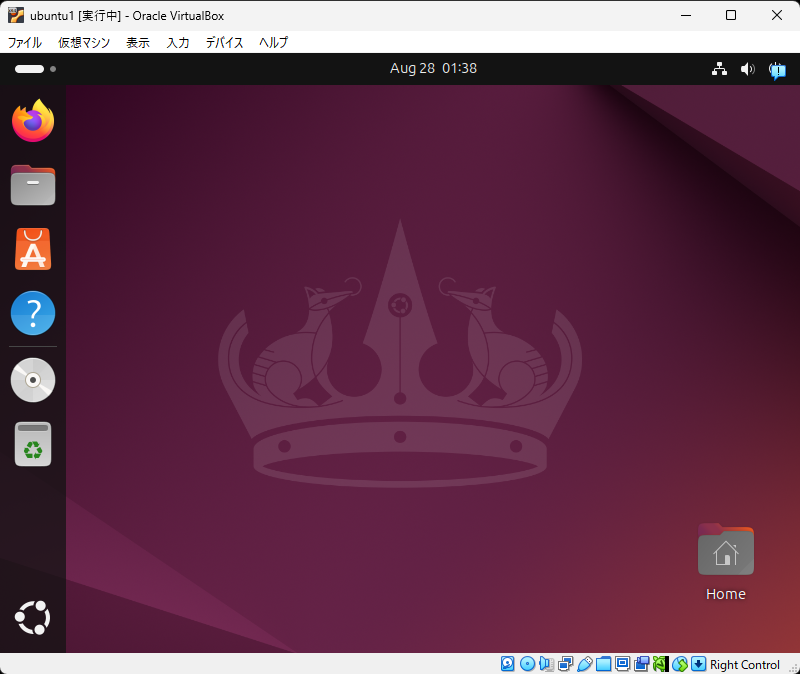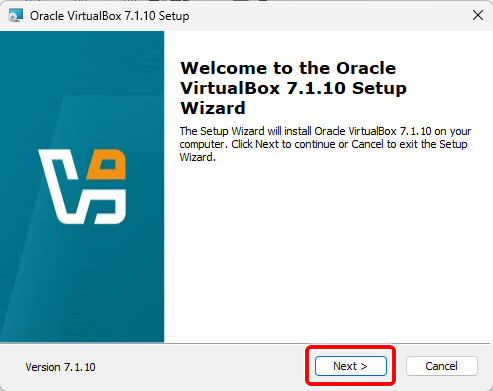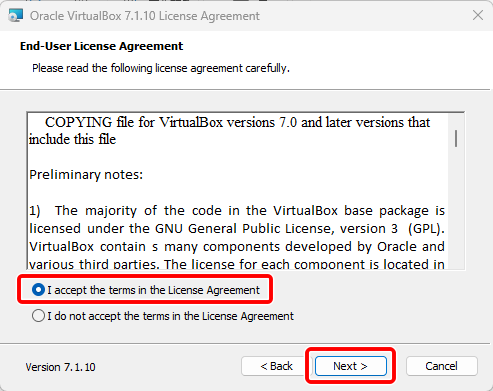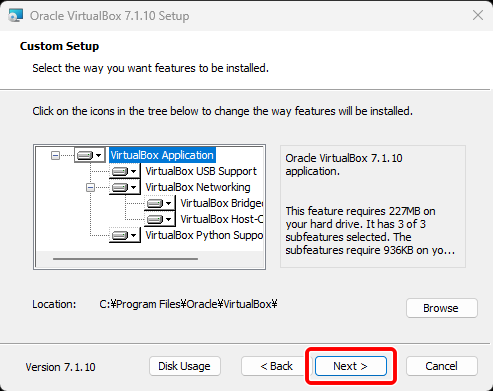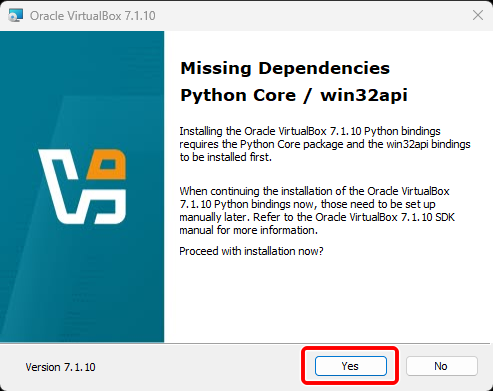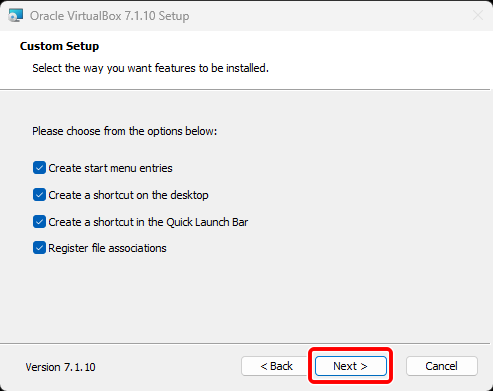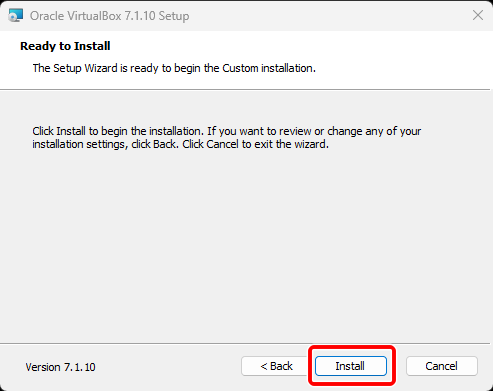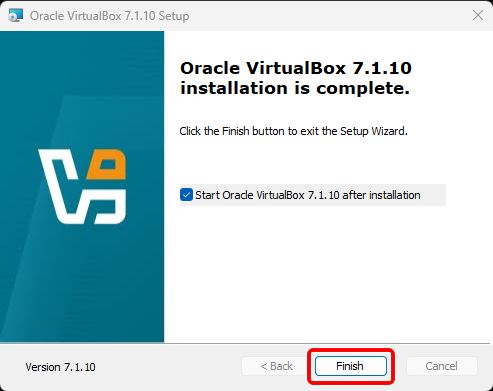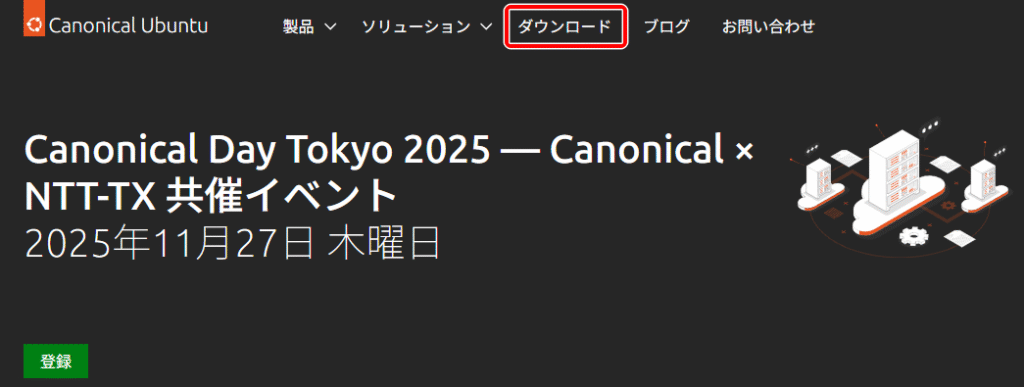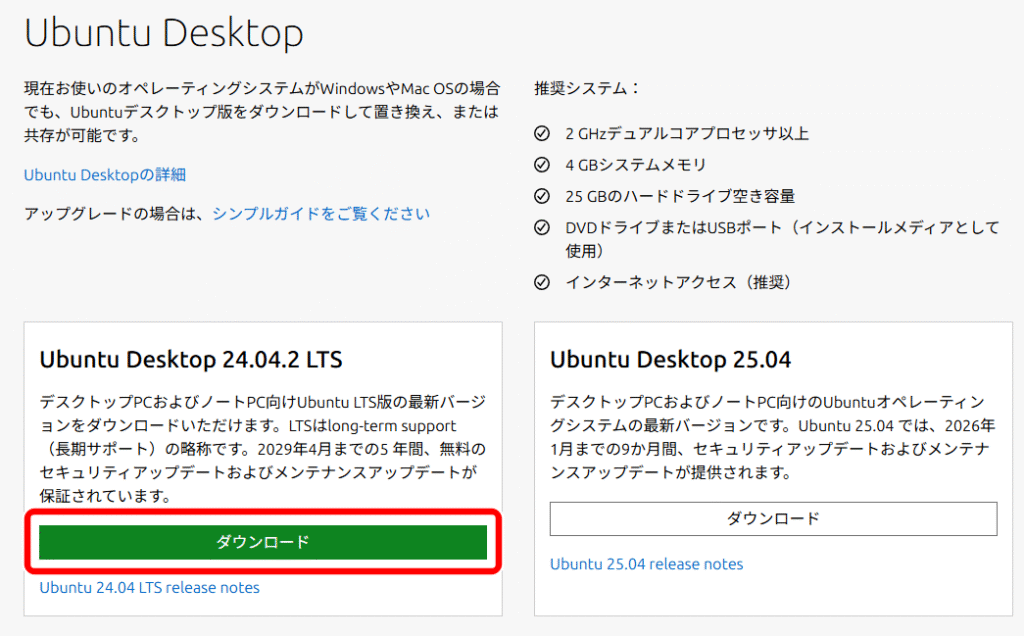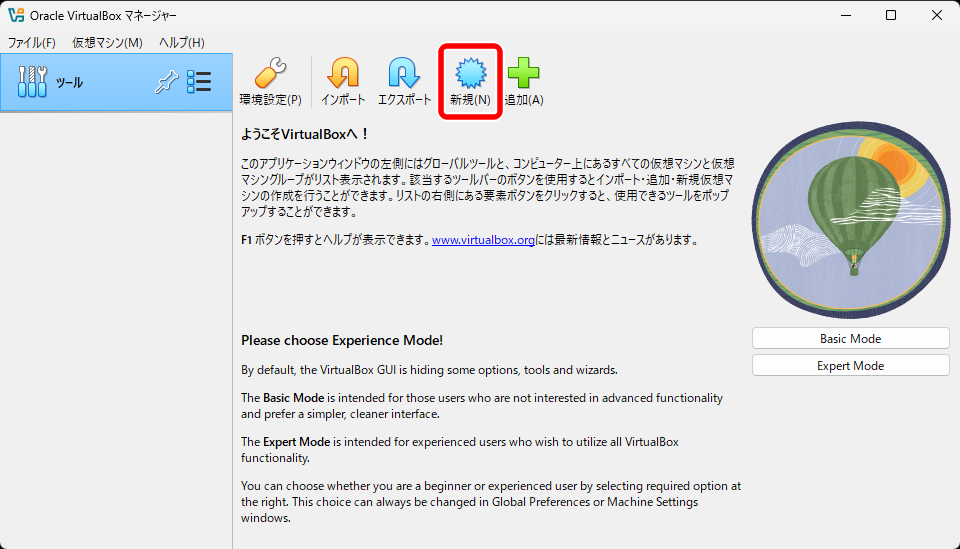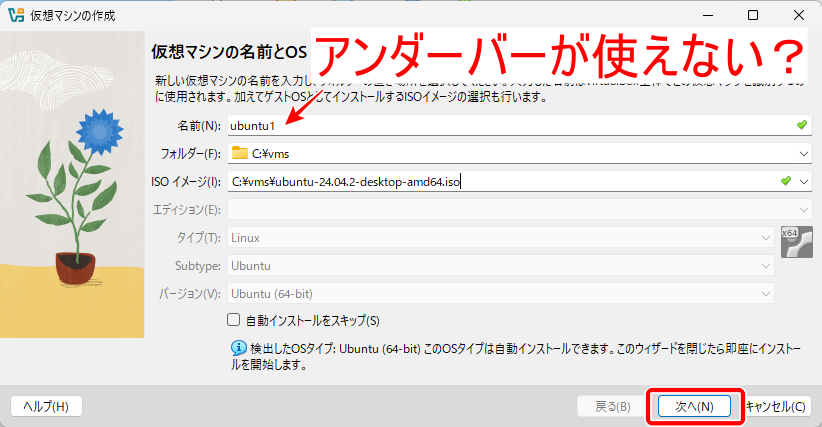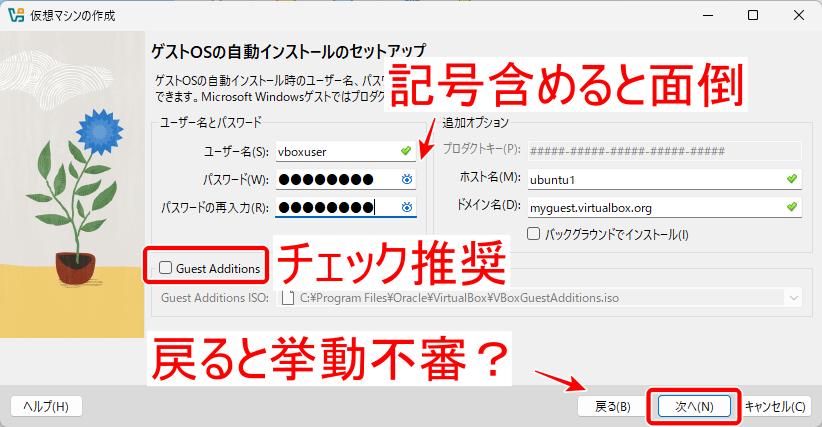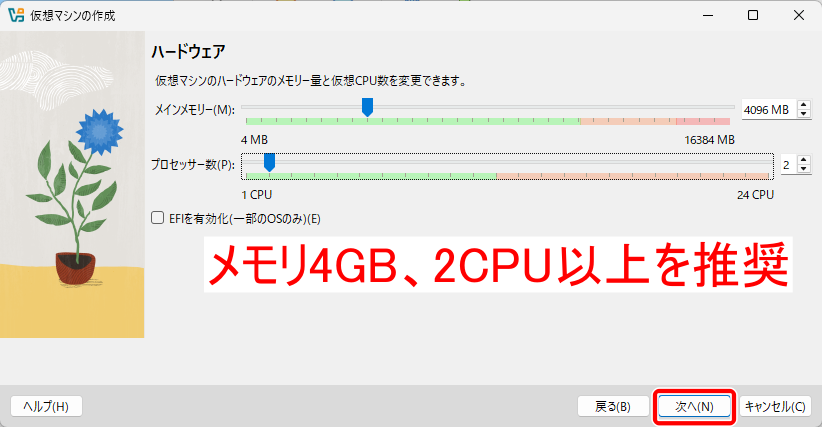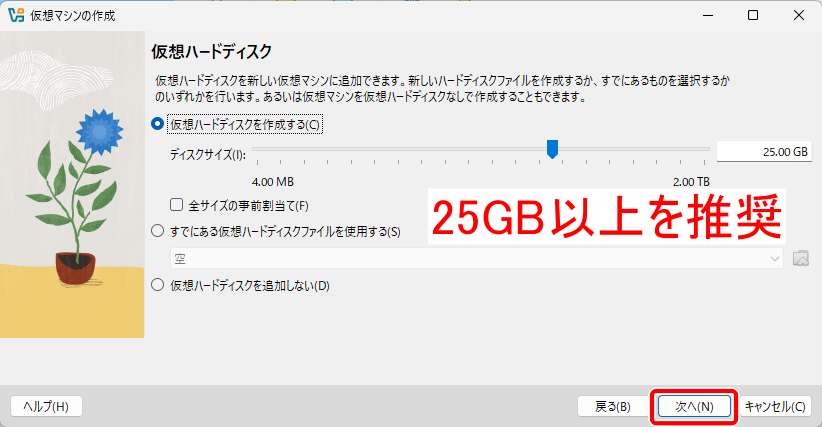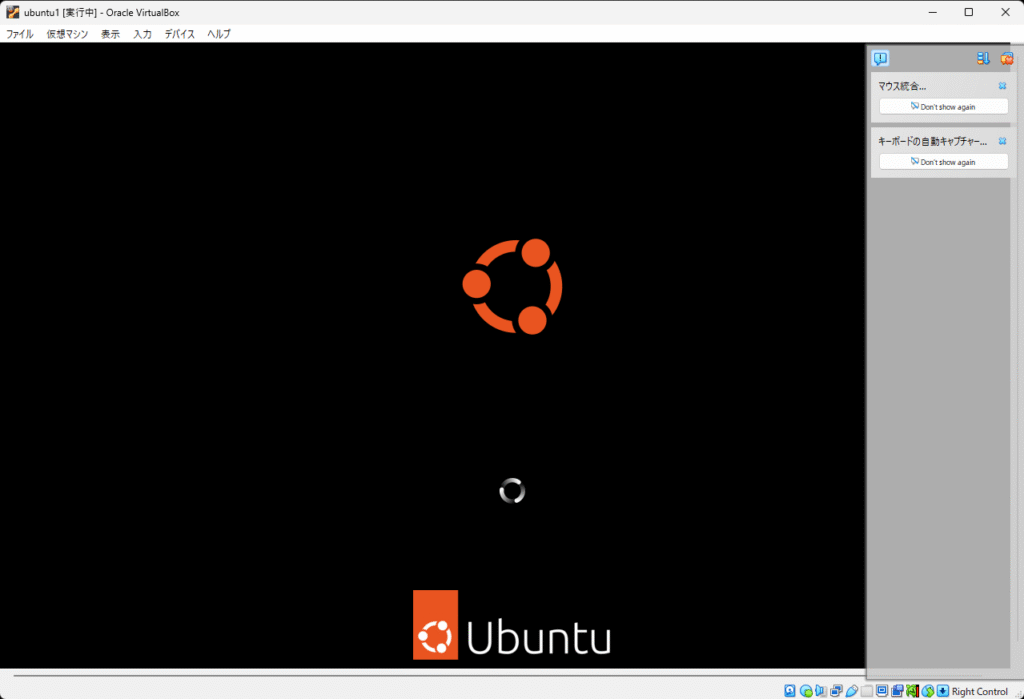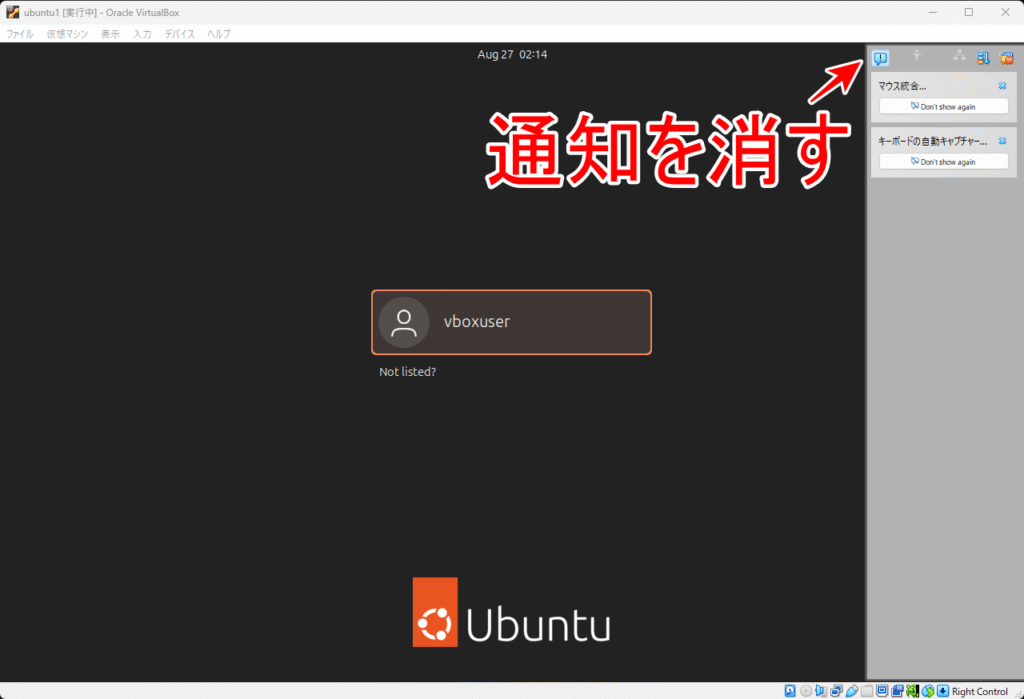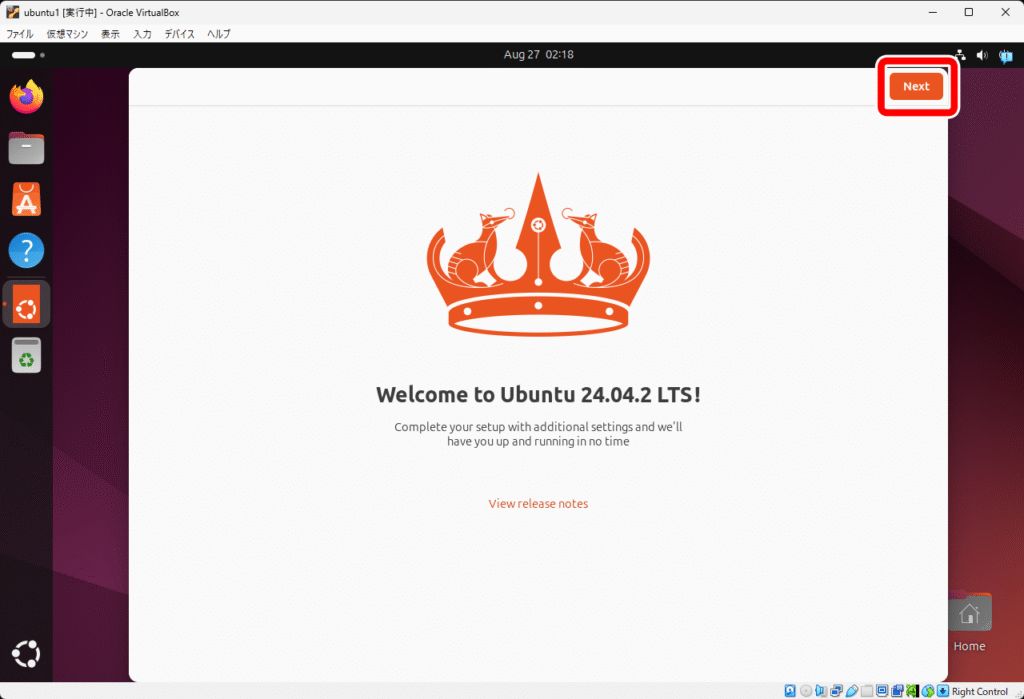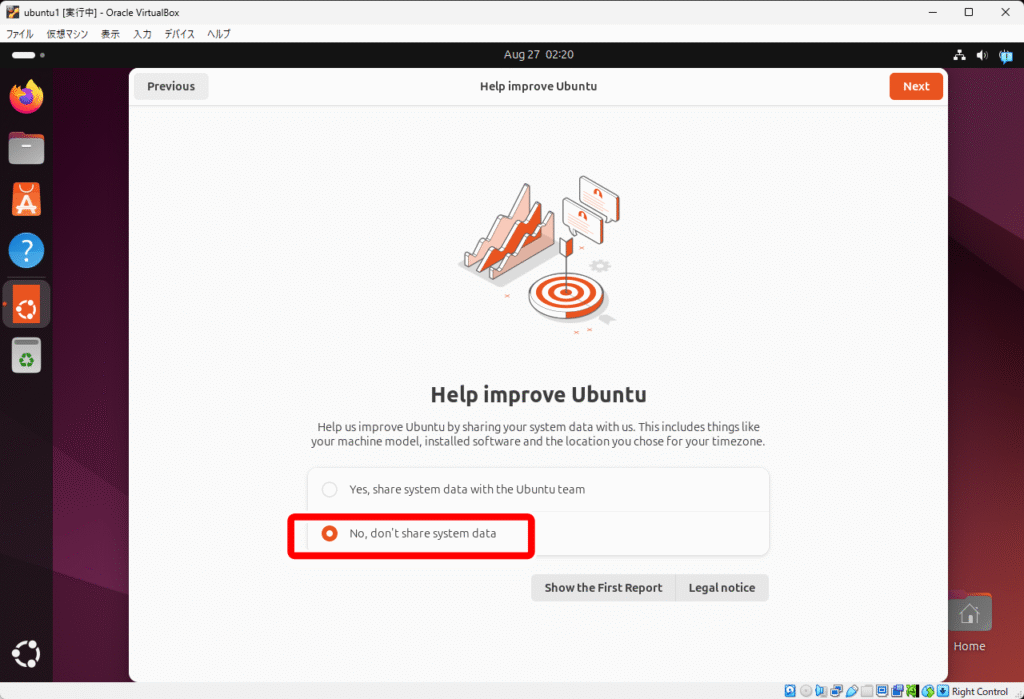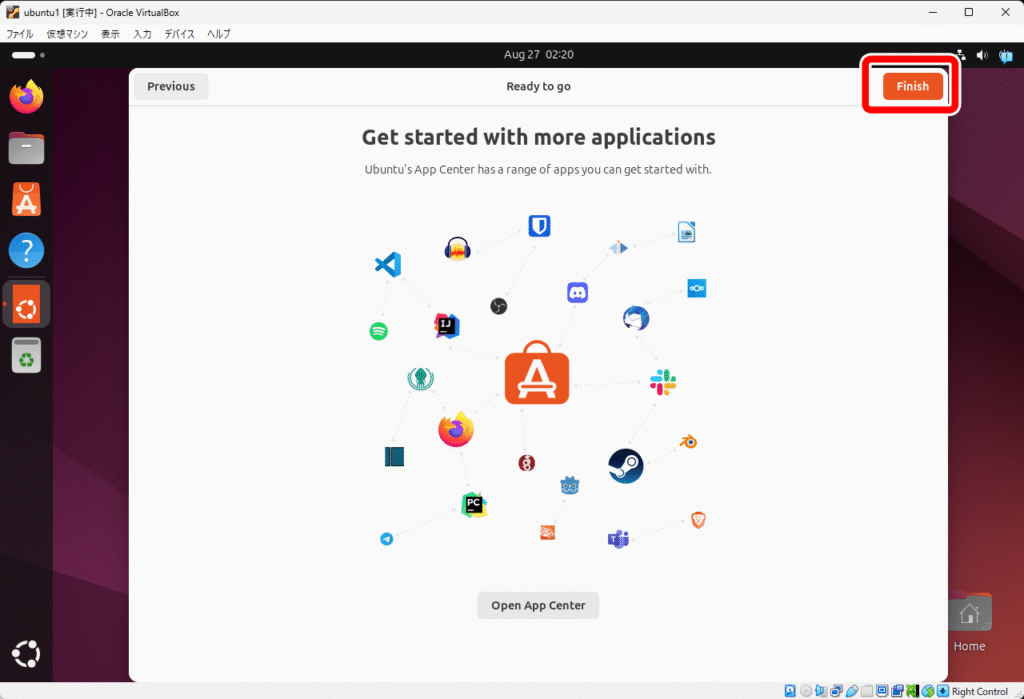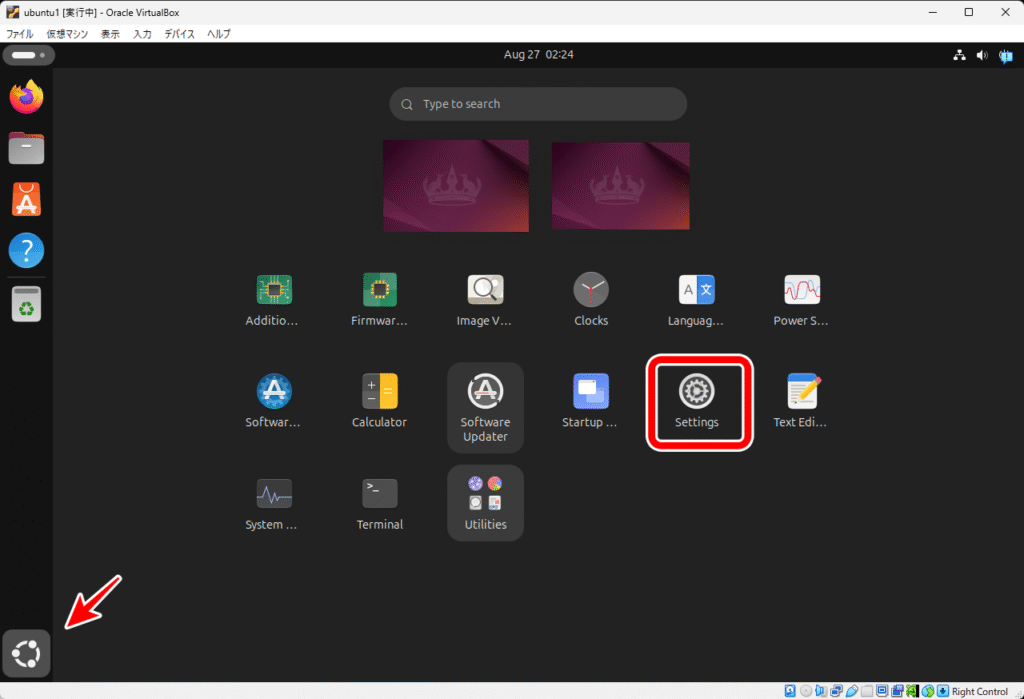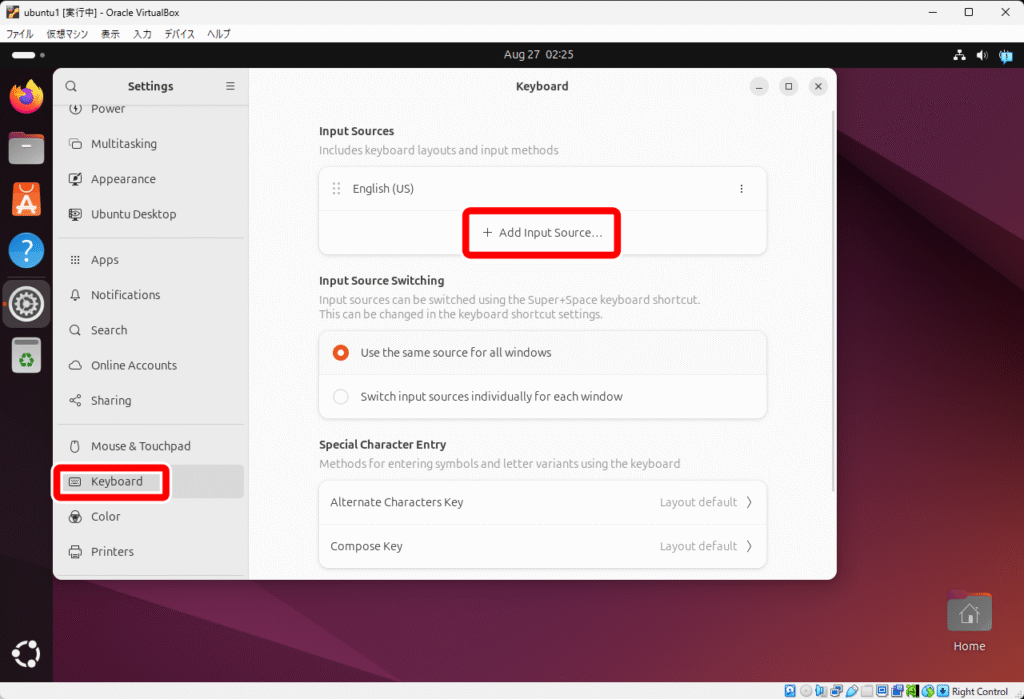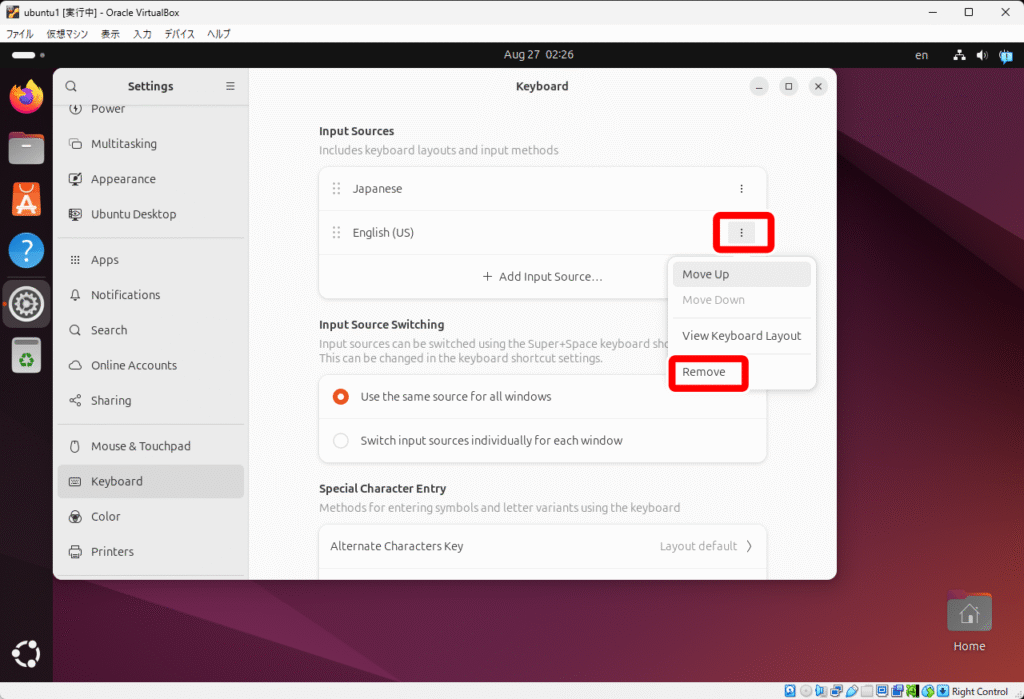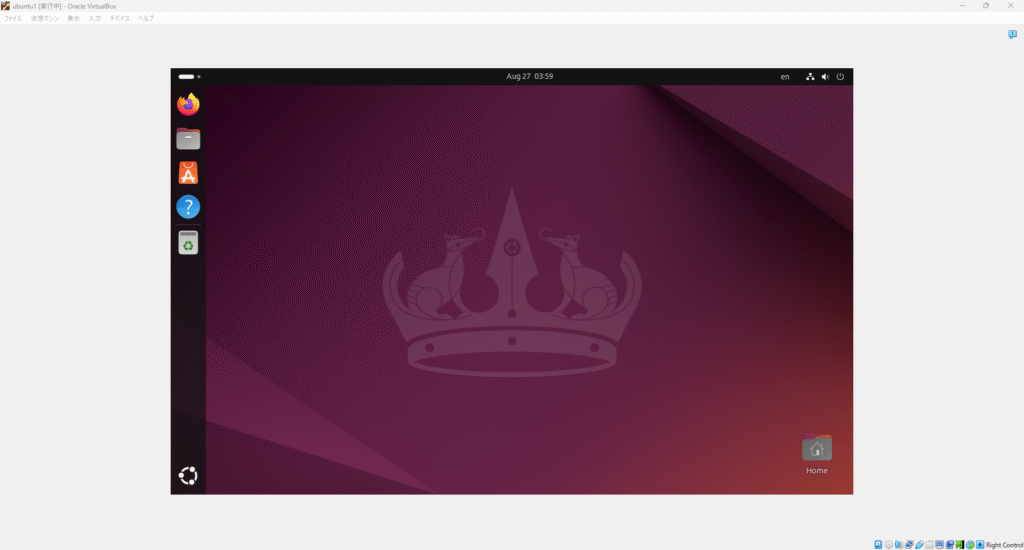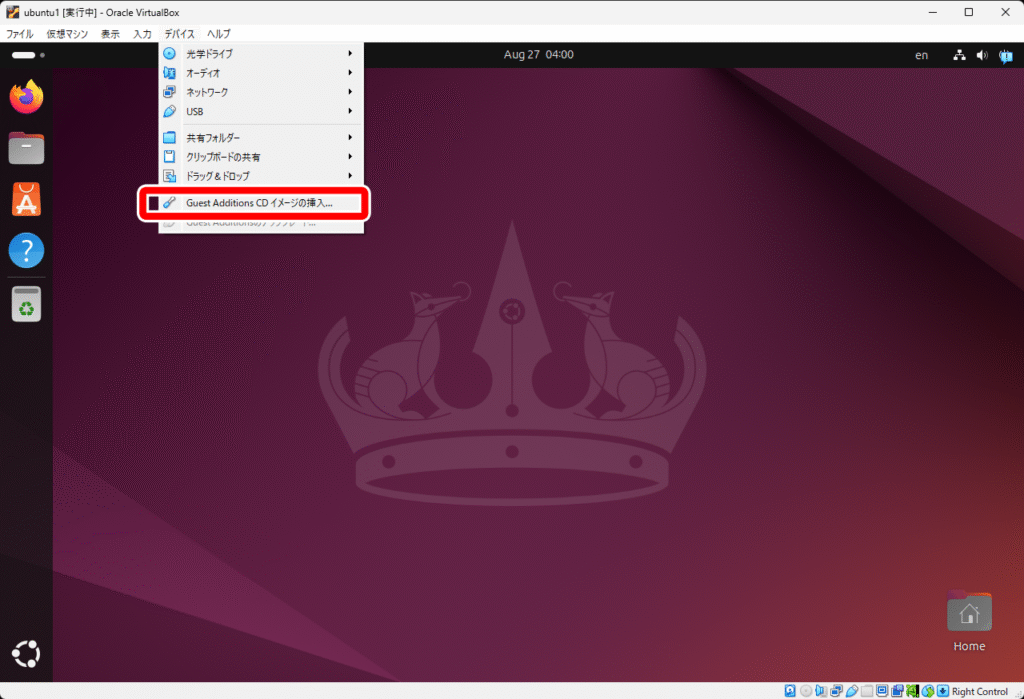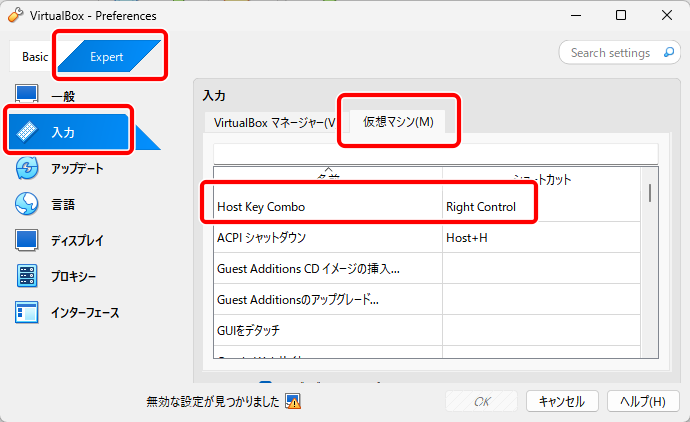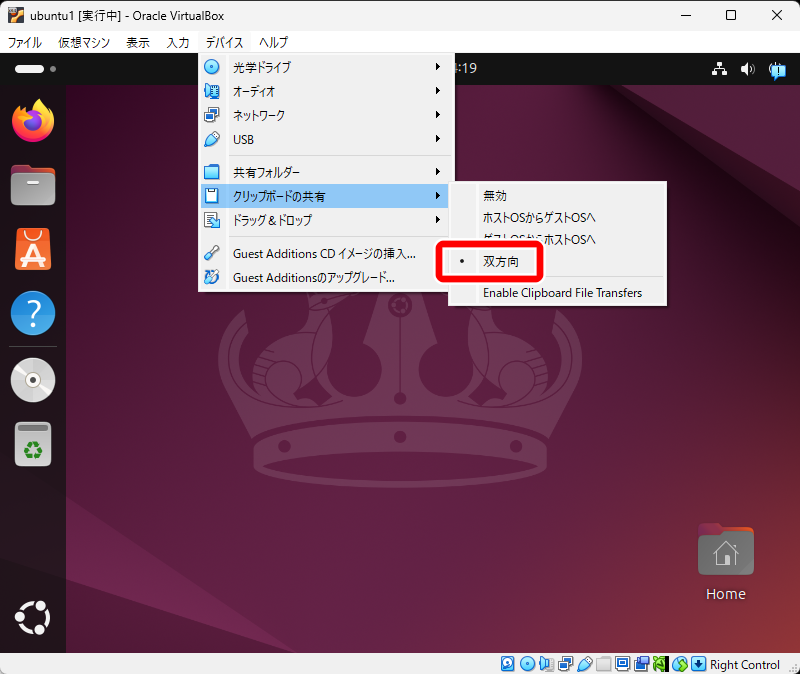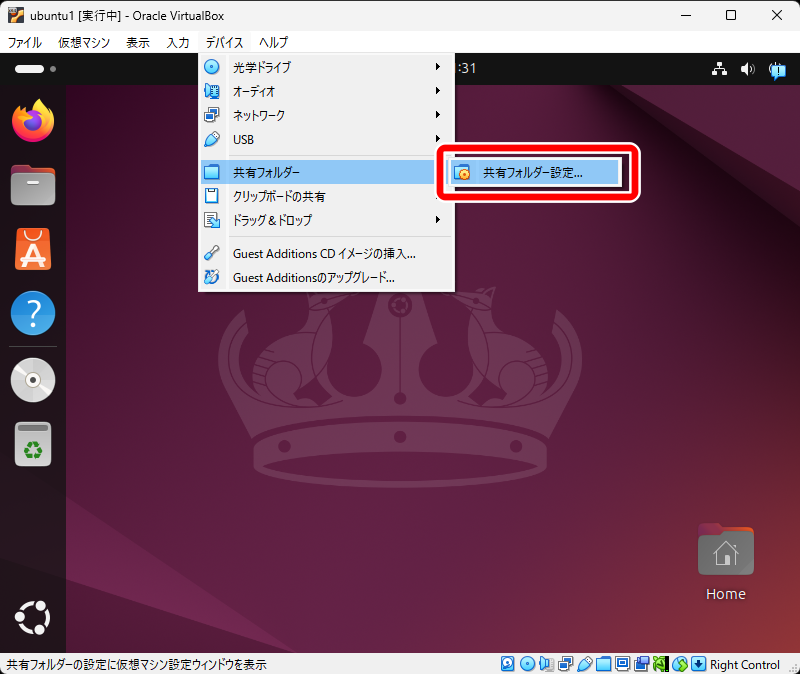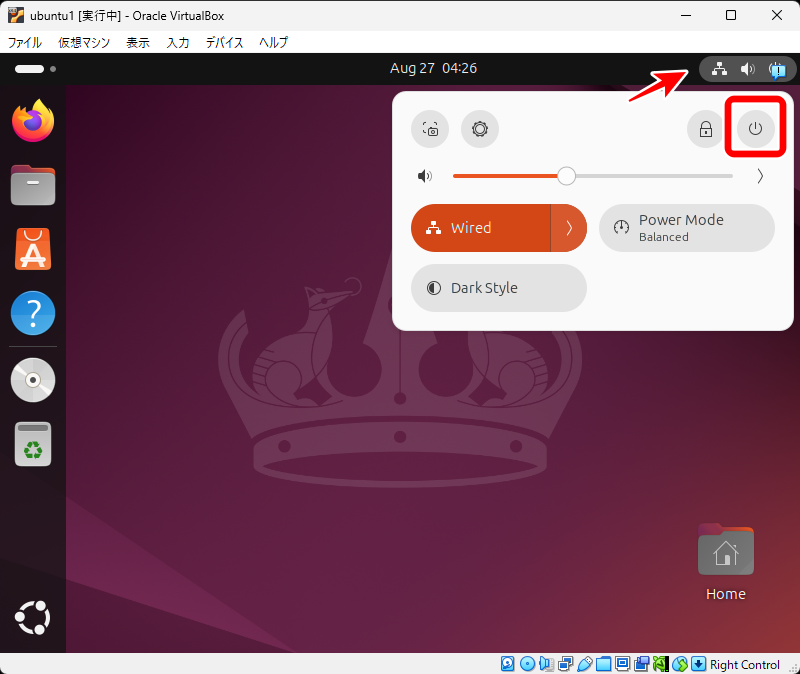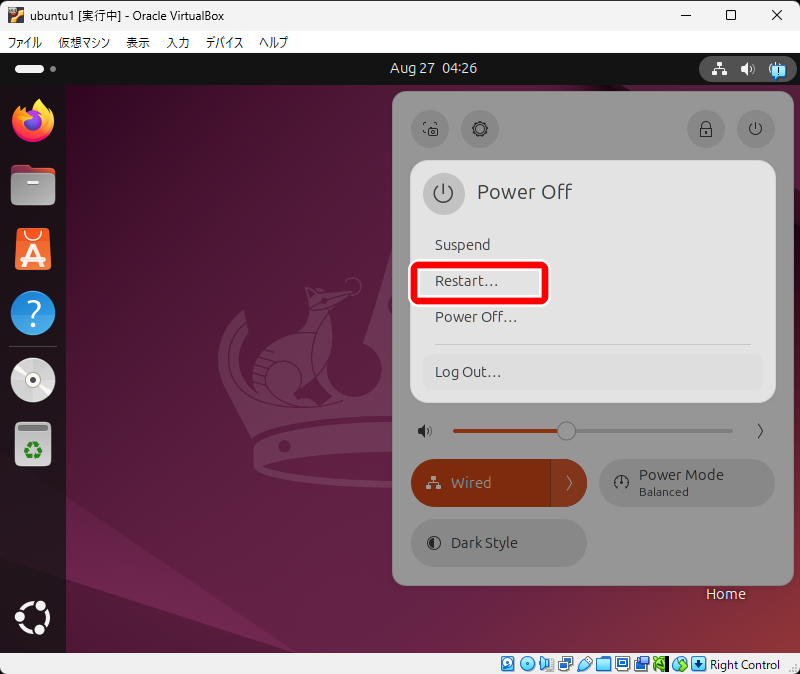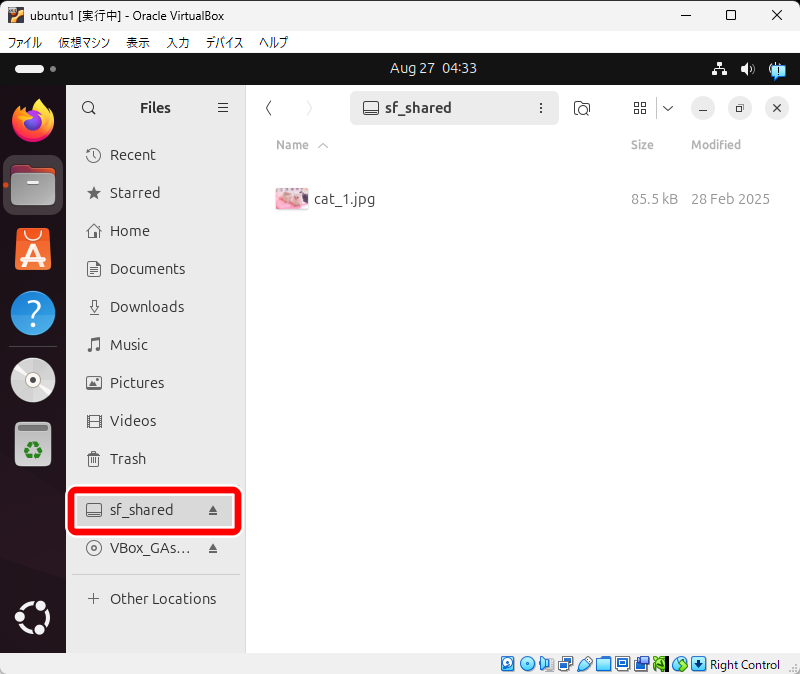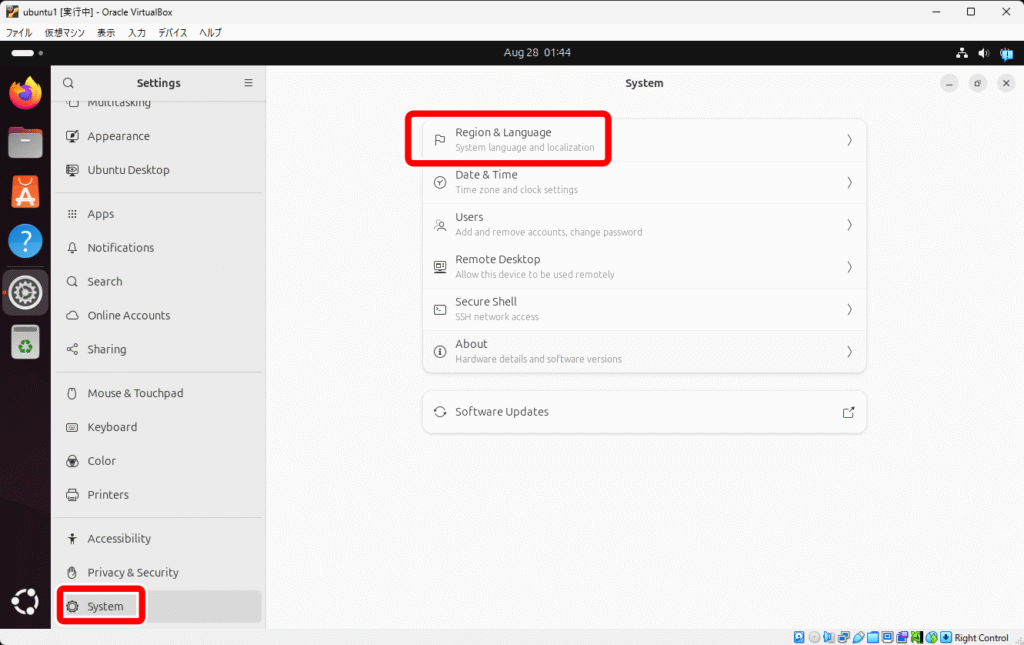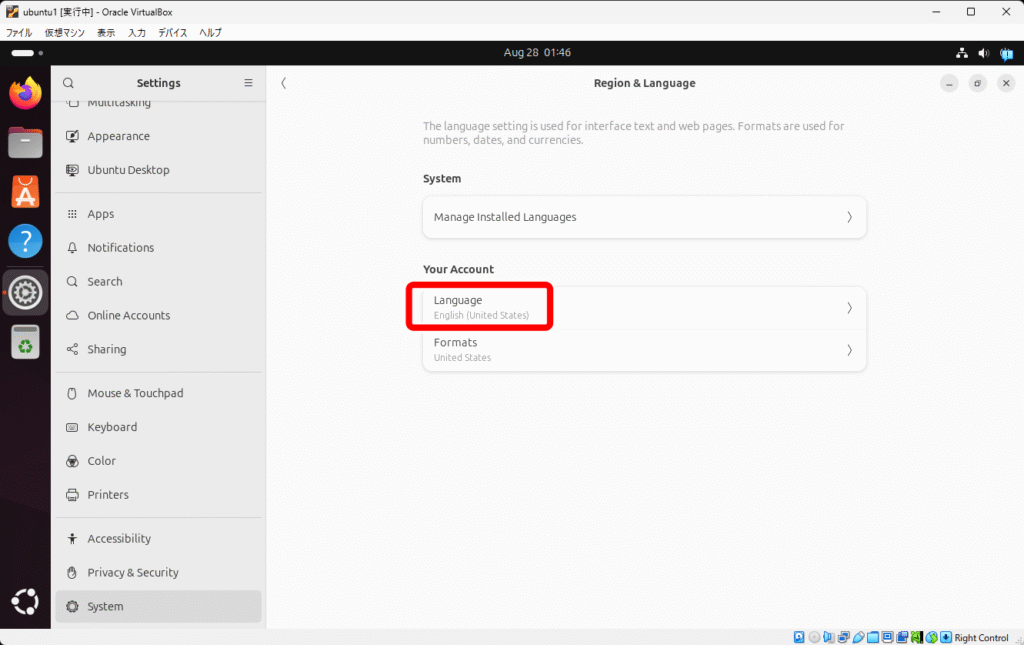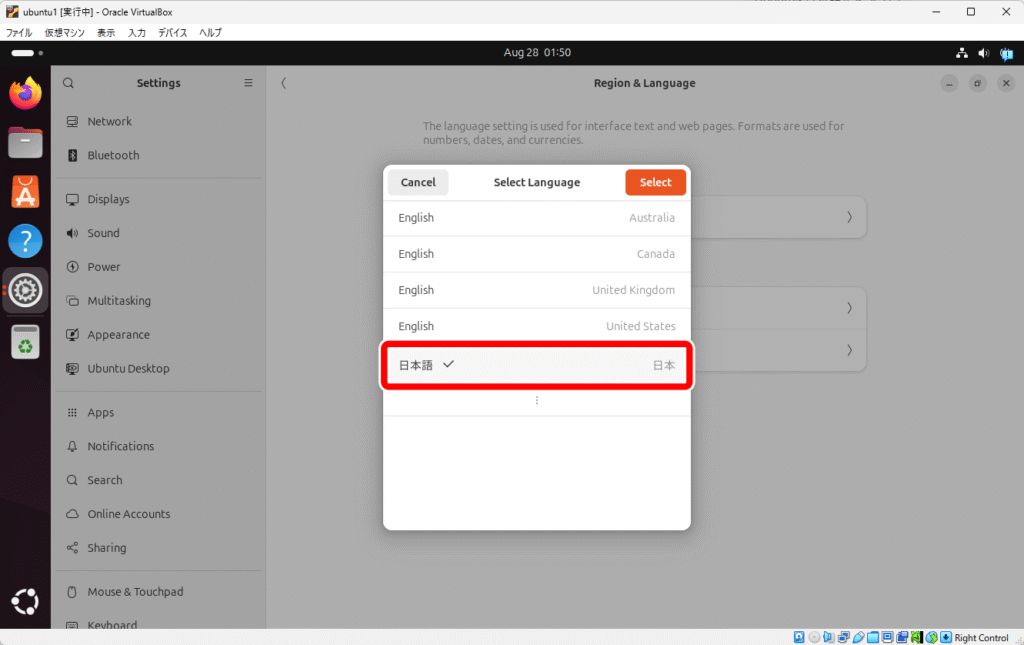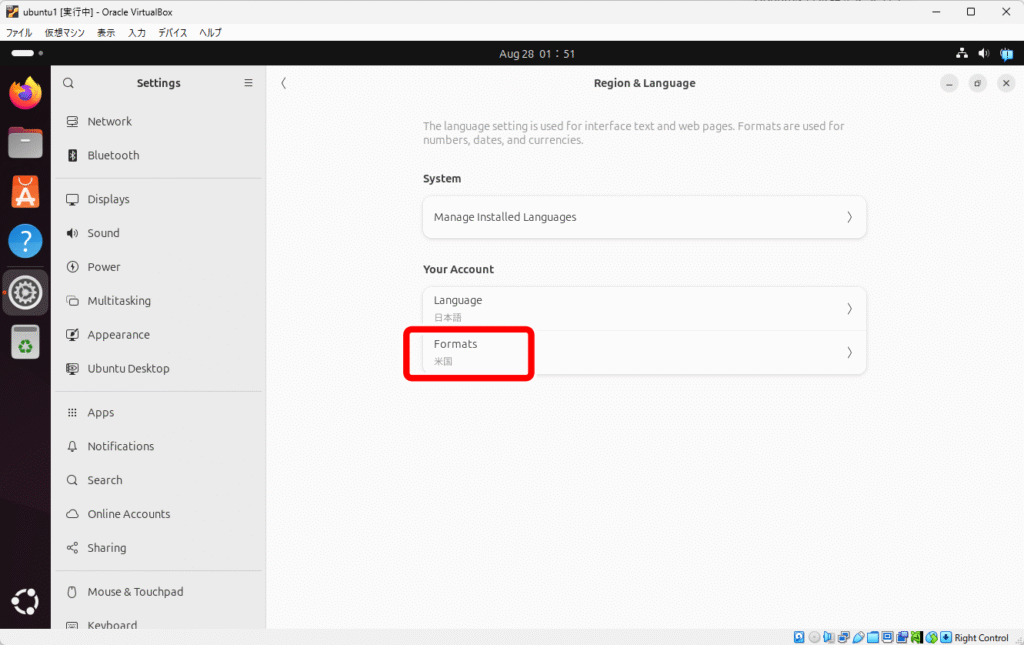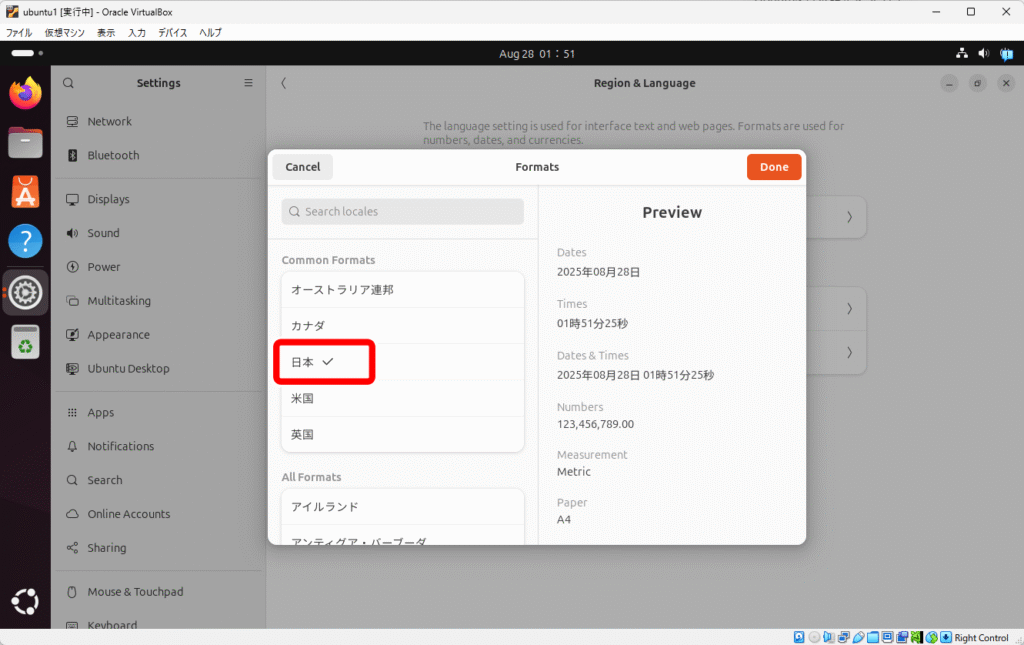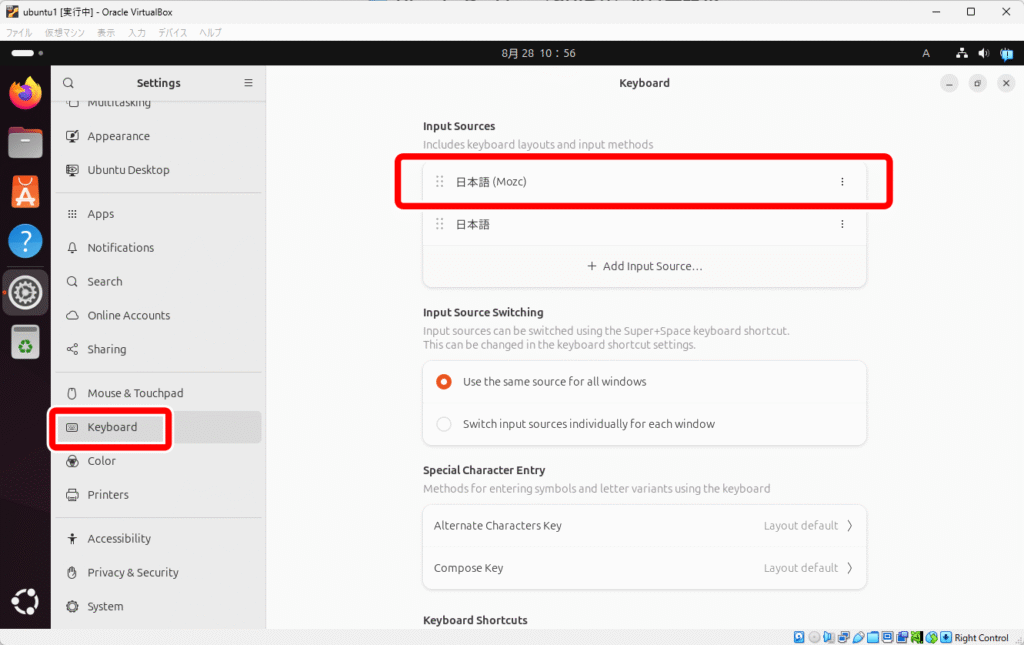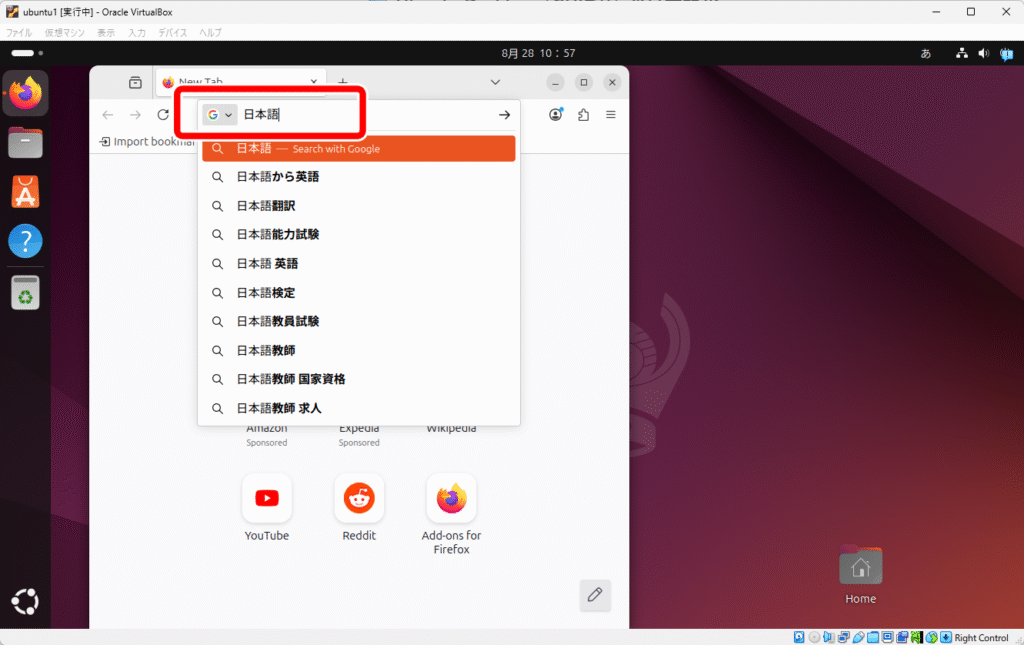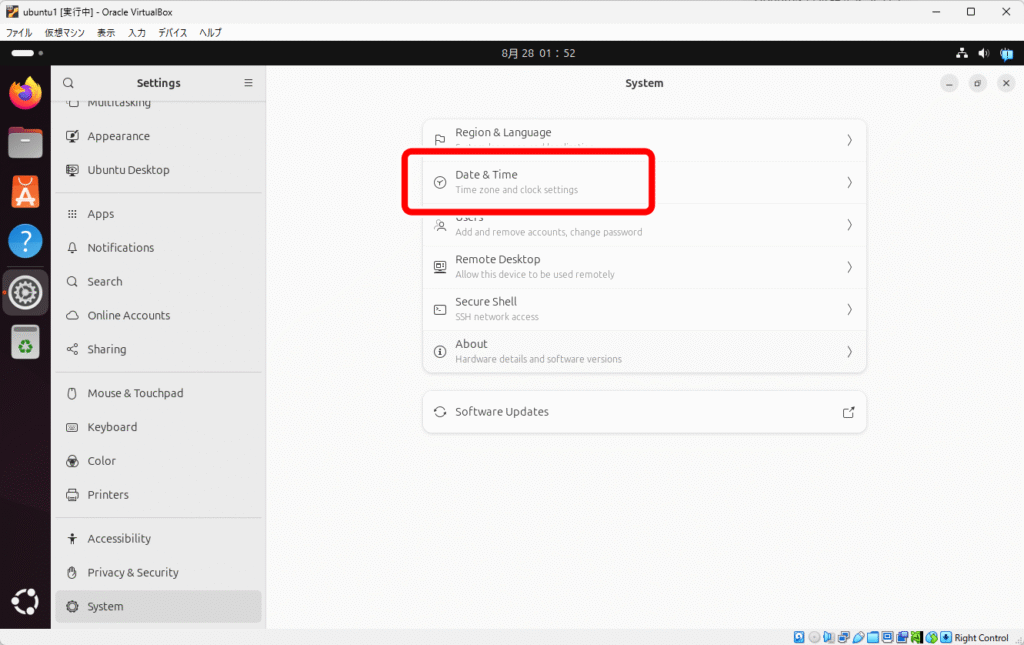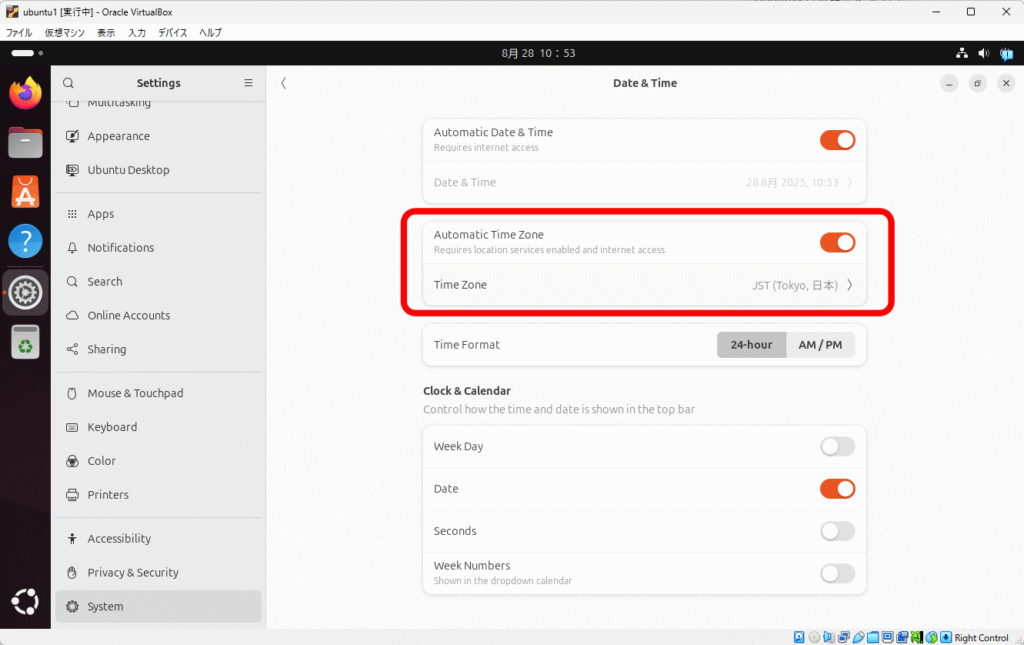VirtualBoxを使えば、Windows上に簡単にLinux環境を作ることができます。Linuxの使い方はともかくとして、セットアップまでであれば、それほど難しくはありません。この記事では、Windows 11にVirtualBoxをインストールし、その上でUbuntuを動かす方法をご紹介します。またUbuntuを日本語で使うための、基本的な設定についても解説しています。
VirtualBoxとUbuntuの概要
- VirtualBoxとは
- 無料で利用できる? 商用利用は?
- 推奨スペックは?
- プライバシー保護に役立つ?
- Ubuntuとは
VirtualBoxとは
「VirtualBox」とは、Oracle社が提供する仮想化ソフトで、ホストOS上で、別のゲストOSを実行することができます。
例えば、Windows上でLinuxを実行したり、その逆をしたりすることができます。
オープンソースで開発されており、個人であれば無料で利用することができます。
歴史
VirtualBoxは、2007年にドイツのinnotekにより開発されましたが、2008年にSun Microsystemsがinnotekを買収しました。
さらに2010年にOracleがSun Microsystemsを買収したことにり、現在はOracleが管理しています。
無料で利用できる? 商用利用は?
VirtualBoxのライセンスは、本体部分と、Oracleが開発した拡張パック部分により異なります。
拡張パックには、USB対応、リモートデスクトップ接続、ディスク暗号化などの便利な機能が含まれています。
- 本体: GPLv3
- 拡張パック: PUEL
GPLv3(GNU General Public License v3)は、無料で利用でき、改変・商用利用も可能だが、再配布する場合は同じくGPLv3にする必要があるというものです。
PUEL(Personal Use and Evaluation License)は、個人・教育・評価利用は無料だが、商用利用する場合はOracleとライセンス契約が必要というものです。
基本的には、個人であれば無料、会社等の組織で利用する場合は有料と考えておけばよいでしょう。
推奨スペックは?
用途にもよりますが、ホストPCの推奨スペックは以下のとおりです。
- CPU: 4コア以上(Intel Core i5 / Ryzen 5以上)
- メモリ: 8GB以上
- ストレージ: 50GB以上を確保
- GPU: 内蔵で十分
プライバシー保護に役立つ?
プライバシー保護やセキュリティを考えると、結局Windowsを使用している限り限界があるという結論となります。
代わりとして、Linuxを利用するという方法がありますが、一から準備をするのは大変です。
それであれば、VirtualBox等の仮想マシン上でLinuxを動かせばどうかということなのですが、効果としては限定的でしょう。
ネットワーク通信はホストPCを通るので、その監視を逃れることはできませんし、Recallは画面全体のスクリーンショットを取得します。
ただ、テスト環境を作ったり、ちょっと使いたいアプリがあるという場合にはとても便利です。
慣れたら、中古PC等にLinuxをインストールすることをおすすめします。
Ubuntuとは
「Ubuntu」とは、Linuxディストリビューション(パッケージ)の一つです。
Ubuntuは、Linuxディストリビューション全体の30~40%を占めると言われており、現在一番人気が高いものです。
プライバシー保護を考えるならば、「Tails」や「Qubes」というディストリビューションもありますが、今回はVirtualBoxの紹介なので、一番人気のUbuntuを採用しました。
VirtualBoxにUbuntuをインストールする方法と日本語設定
- Windows 11にVirtualBoxをインストール
- VirtualBoxにUbuntuをインストール
- キーボードレイアウトの変更
- フルスクリーン
- フルスクリーンの解除
- コピペ共有
- 共有フォルダ
- 日本語化
- 日本語入力の設定
- 日時設定
Windows 11にVirtualBoxをインストール
「Oracleのサイト」または「virtualbox.org」からインストーラーをダウンロードします。
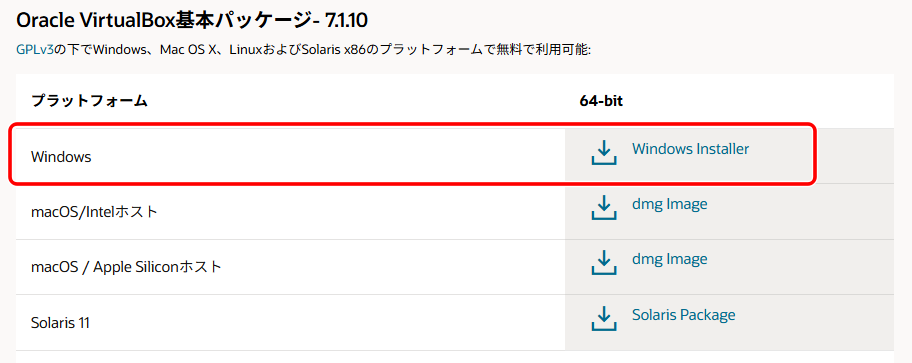
ダウンロードしたファイルを実行し、「Next」をクリックします。
ライセンス内容を確認し、「Next」をクリックします。
インストールする機能を選択します。
- VirtualBox Application:本体(必須)
- USB Support: ホストPCに接続したUSBデバイスを、ゲストPCで使用できるようにする
- Networking: ネットワーク関連機能
- Bridged Networking: LAN内の別のPCから、ゲストPCに接続できる
- Host-Only Networking: ホストとゲストのみで通信をし、外部に接続しない
- Python Support: PythonからAPIで操作できるようにする
Python Supportは外してもいいですが、全選択のままでも特に問題はありません。(後述)
通信が一時的に切断されるという警告です。
「Yes」をクリックします。
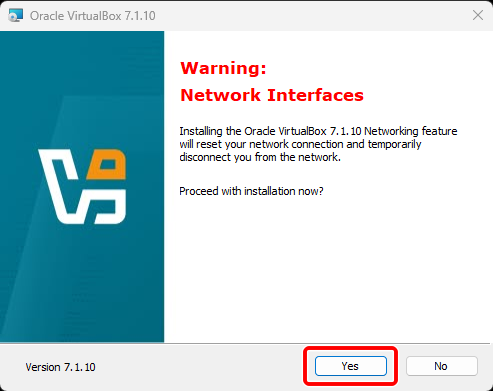
「Python Support」が選択されたが、「Python Core」と「win32api」がインストールされていないので、使えないという警告です。
使いたければ、後から手動設定する必要があります。
とりあえず使う予定はないので、「Yes」をクリックします。
ショートカットの作成や、ファイルの関連付けの選択をします。
ファイルの関連付けは、拡張子「.vbox」や「.vdi」をダブルクリックで開けるというものですが、チェックを外しても特に問題ありません。
「Install」をクリックし、しばらく待ちます。
「Finish」をクリックし、完了です。
VirtualBoxにUbuntuをインストール
次に、VirtualBox上に、ゲストOSとしてUbuntuをインストールする方法をご紹介します。
ダウンロード
まず、UbuntuのISOファイルをダウンロードします。
「https://jp.ubuntu.com/」を開き、「ダウンロード」をクリックします。
「ダウンロード」をクリックします。
最初は、サポートの長い「LTS」の方をおすすめします。
仮想PCの設定
VirtualBoxを起動し、「新規」をクリックします。
仮想PCの「名前」を決めます。
この時に、名前に「_(アンダーバー)」が使えないようでした。
どこにもそのような説明はないし、ネット上で同じような人は見当たらなかったのですが、私が試した限りはそのように思えました。
保存フォルダーを決め、ダウンロードしたISOファイルを選択し、「次へ」をクリックします。
次の画面で、ユーザー名とパスワードを決めるのですが、ここで「戻る」とすると、挙動不審になるようでした。
上手くいかない場合は、キャンセルして最初からやり直すことをおすすめします。
パスワードは、キーボードレイアウトの違いにより、記号を含めると意図したとおりに出力されない可能性があります。
最初は記号無しで作っておいた方が、面倒が少ないです。
「Guest Additions」は、フルスクリーンやクリップボード共有を可能とする、便利機能です。
チェックを入れることを推奨しますが、今回は説明のために、あえてチェックなしとしています。
割り当てるメモリとCPU数を設定します。
Ubuntuの場合、メモリ4GB以上、CPU2以上が推奨されています。
「EFIを有効化」とは、BIOSをEFIに置き換えるかどうかということで、普通は必要ないと思います。
仮想ハードディスクは、25GB以上が推奨されています。
用途にもよりますが、ホストPC上に共有フォルダを作成することもできるので、そこまで必要はないと思います。
設定内容を確認し、「完了」をクリックします。
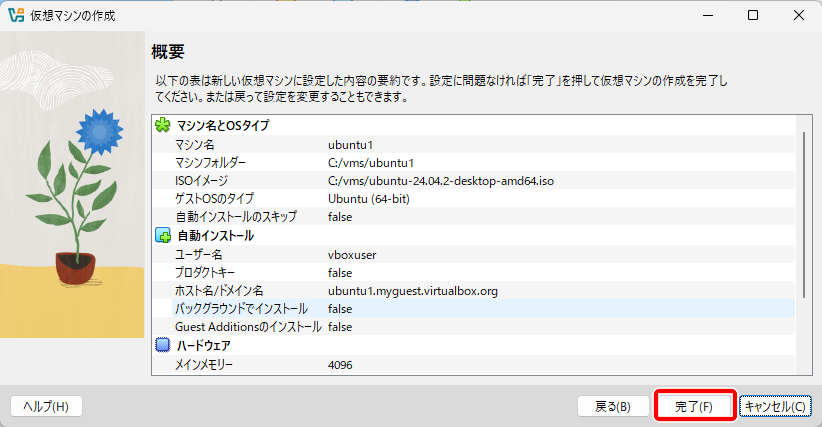
インストール
自動的にUbuntuのインストールが始まるので、しばらく待ちます。
このようなログイン画面となれば完了です。
右の通知領域が邪魔であれば、「i」で隠すことができます。
ログインすると、初回はこのような画面となります。
「Next」をクリックします。
Canonical社が提供する、拡張サポートサービス「Ubuntu Pro」に加入するかの確認です。
個人であれば無料で加入できます。
とりあえず「Skip」とします。
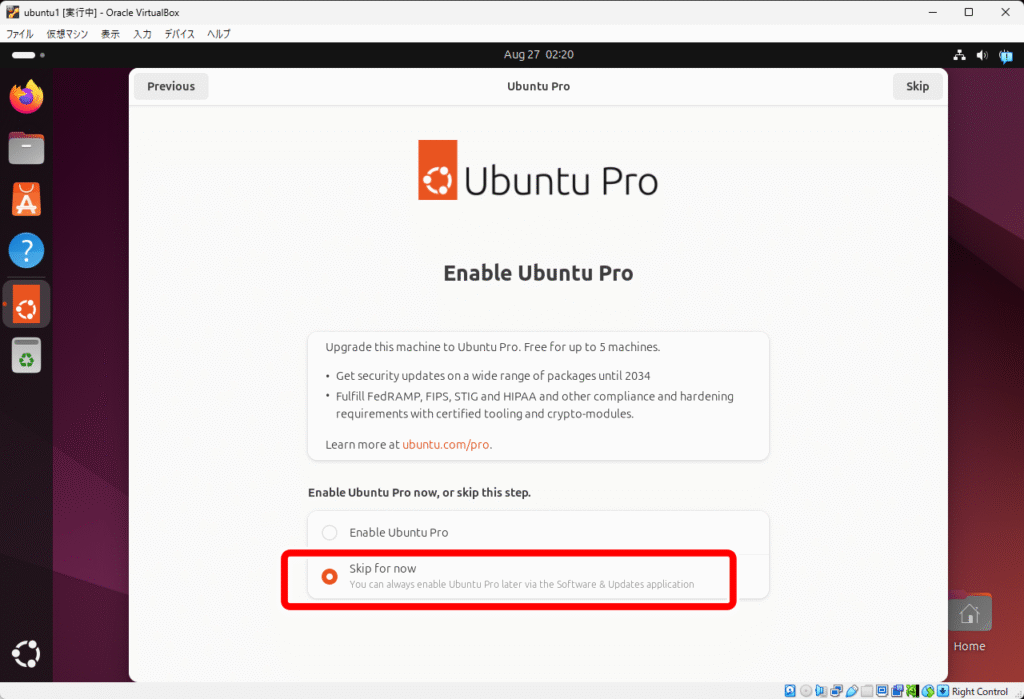
利用状況の収集の確認です。
「No」とします。
「Finish」をクリックして完了です。
キーボードレイアウトの変更
初期設定では、キー配列が英語キーボードとなっているので、日本語キーボードを使用している場合は、記号の位置が異なる可能性があります。
左下のアイコンから「Settings」を開きます。
「Keyboard」から、「Add input Source」をクリックします。
「Japanese」を追加します。
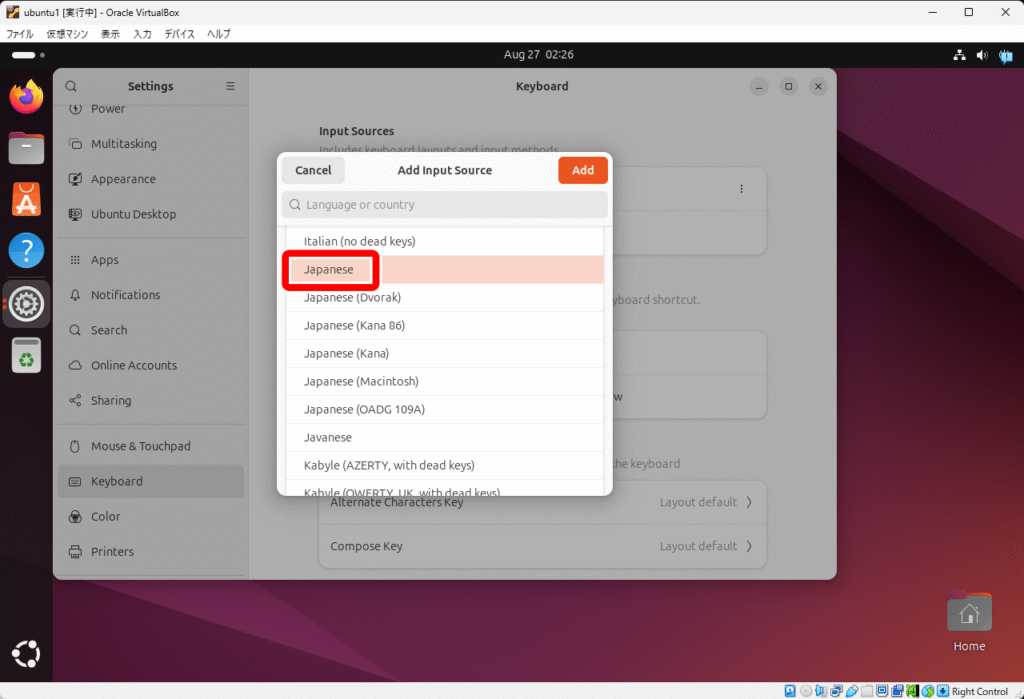
「English(US)」横の「⋮」をクリックし、「Remove」します。
フルスクリーン
「Guest Additions」をインストールしていない場合は、画面をフルスクリーンにすることができません。
以下のように、VirtualBoxの画面を広げても、中のUbuntuの画面が広がりません。
「Guest Additions」を後からインストールするには、まず「デバイス」から「Guest Additions CDイメージの挿入」をクリックします。
ターミナルを起動し、以下のコマンドを順番に実行します。
パッケージを最新に更新する。
sudo apt update必要な開発ツールをインストールする。
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)「Guest Additions CD」のインストーラーを実行する。(パスはユーザー名やバージョン番号により異なります)
sudo sh /media/vboxuser/VBox_GAs_7.1.101/VBoxLinuxAdditions.runその後、画面サイズを自由に変更できるようになります。
フルスクリーンも可能です。
フルスクリーンの解除
フルスクリーンモードを解除するには、「右Ctrl + F」です。
Hostキーを別のキーに割り当てている場合は、VirtualBoxの「環境設定」-「Expert」-「入力」-「仮想マシン」でご確認ください。
コピペ共有
「Guest Additions」をインストールした後であれば、ホストPCとゲストPC間で、コピペ(クリップボード)を共有できます。
「デバイス」-「クリップボードの共有」-「双方向」にチェックを入れます。
共有フォルダ
ホストPCのデータをゲストPCから参照するには、ホストPCに共有フォルダを作成し、ゲストPCでマウントするという作業が必要です。
「デバイス」-「共有フォルダー」-「共有フォルダー設定」をクリックします。
「共有フォルダー」の「+」アイコンをクリックします。
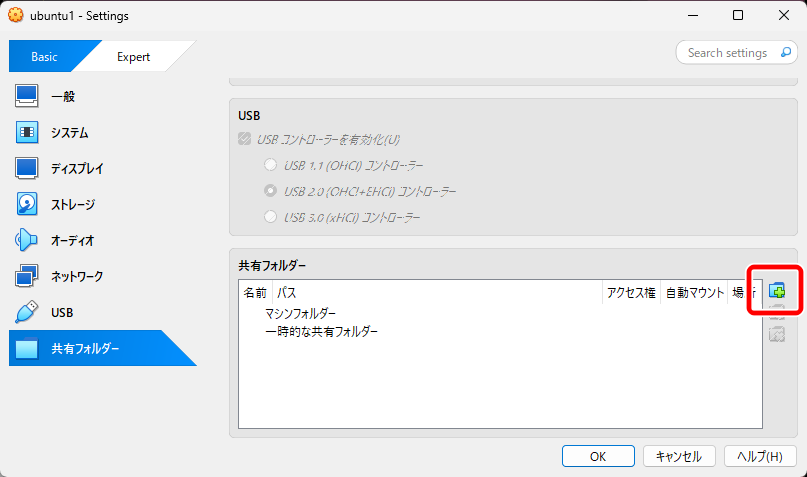
フォルダーのパスを入力します。
「自動マウント(起動時に自動マウント)」と「永続化する(再起動しても設定を保持)」は、チェックを入れたほうが便利だと思います。
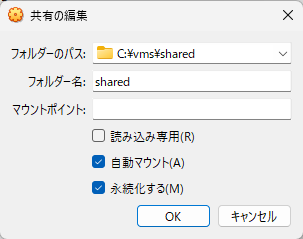
このままではアクセス権がないので、ユーザーを共有フォルダグループに追加する必要があります。
ターミナルで、以下のコマンドを実行します。
sudo usermod -aG vboxsf $USER設定を反映させるために、ゲストPCを再起動させます。
右上のシステムメニューをクリックし、電源アイコンをクリックします。
「Restart」をクリックします。
再起動後、「sf_【共有フォルダ名】」が自動マウントされ、中のファイルにアクセスできるようになります。
日本語化
システム言語を日本語にするには、まず日本語パッケージをインストールする必要があります。
ターミナルで以下のコマンドを実行します。
sudo apt install language-pack-ja次に、「Settings」-「System」-「Resion & Language」をクリックします。
「Language」をクリックします。
「日本語」を選択します。
設定を反映されるには、ログアウト/再ログインが必要となります。
同様に、「Fromats」をクリックします。
「日本」を選択します。
こちらも再ログインが必要となります。
日本語入力の設定
上記でキーボードレイアウトを変更しましたが、それはただの配列であって、日本語変換ができません。
日本語変換できるようにするには、ターミナルで以下のコマンドを実行します。
sudo apt install ibus-mozc再ログインをし、「Input Sources」に「日本語(Mozc)」が追加されていることを確認します。
日本語変換できるようになりました。
日時設定
初期設定では、タイムゾーンがズレているので、時刻があっていないと思います。
「Settings」-「System」-「Date & Time」をクリックします。
「Time Zone」で「Tokyo, 日本」を選択し、「Automatic Time Zone」をオンにします。
まとめ VirtualBoxとUbuntuのインストールと基本設定
Windows 11にVirtualBoxをインストールし、そのゲストPCとしてUbuntuをインストールする方法をご紹介しました。
またUbuntuを日本語で使うための、基本的な設定をご紹介しました。
プライバシー保護を考えると、どうしてもWindowsでは限界があり、Linuxを利用する必要がでてきます。
VirtualBoxのような仮想環境では、効果は限定的ですが、無料で気軽に試すことができるのでおすすめです。